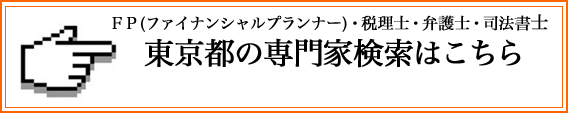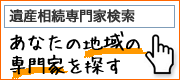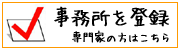自分で遺言書を書く際の注意点
遺言書は、書き方が方式どおりでないと遺言書自体が無効になってしまうケースもあります。
ここでは自分で遺言書を自分で書く際の注意点をあげておきます。
遺言書作成の3つの注意点
遺言書作成の注意点は、3つあります。
- 法的な書式を守る
- あいまいな表現を避ける
- 遺留分の侵害に注意する
順に見ていきましょう。
遺言書の法的な書式を守る
法的な書式とは、「遺言書」として法的に認められるために最低限必要な事項です。以下のような部分に注意して下さい。
- 全て自筆で書く
日付や氏名も全て自筆で記入します(ワープロ等は不可です) - 日付は正確に
年月だけでなく、年月日まで記載します。
何日であるかが確定できれば、「銀婚式の日」のような書き方でも可能ですが、「吉日」のような正確な日付がわからないものは無効となります。 - 加筆・削除した場合はその部分を明確に
加筆・削除その他の変更を加えた場合は、その場所を指示し、変更した旨を付記して署名し、変更の場所に押印します。 - 財産の分割を記載する場合は内容を明確に
あいまいな表現や、誰がどの財産を相続するかがはっきりしないような表現は、後のトラブルの元となります。 - 遺留分に注意
遺留分(法定相続人が法的に認められた最低限の相続権利)を侵害することはできません。遺留分があるため「配偶者がいるのに全ての財産を息子に」とか「息子には一円もやらない!」などということはできません。遺留分を侵害した遺言は無効になってしまうので、遺留分には注意しましょう。相続人ごとの遺留分については図解でわかりやすい相続権の基礎を参考にしてみて下さい。
※法的な書式にそった正確な遺言書の作成には、弁護士や行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。
あいまいな表現を避ける
法的効力を持った遺言書が作成できても、内容があいまいだとトラブルの原因になります。
日本語は、解釈の仕方によっていろいろな意味にとれる言葉があります。せっかく遺言書を作ったのにそれがもとでトラブルに発展したのでは元も子もありません。
遺留分の侵害に注意する
遺留分とは、法定相続人に最低限保障された権利です。この遺留分があるため、遺言を用いても「息子には一切遺産をやらない」といったことはできません。
これらの注意点を守れば、遺言書は自分で作成することができます。
ここで示したポイントをおさえておけば基本的には大丈夫ですが、内容や表現方法は様々なため、実際に書かれた遺言書を見ずに「確実に大丈夫です」とは言えません。
せっかく書いた遺言書が無効になってしまっては取り返しがつきませんので、自筆証書遺言を書いた場合でも、一度専門家に見てもらうことをおすすめします。
遺言書の保管方法
遺言を書いた後は、遺言書を相続人に見つけてもら得る場所に保管しなければなりません。相続人がすぐにわかるような場所で、かつ隠されたり書き換えられたりする心配の無いような場所に保管しておく必要があります。
そのような場所が見つからない場合は、遺言書の保管についてを参考に保管方法を考えてみてください。
遺言書に関する手続きや相談は誰に依頼すればいいの?
トラブルの少ない遺産相続のためにはあらかじめ専門家に遺言の相談をしておくことをおすすめします。わからない点や複雑な手続きは専門家に相談・依頼することが望ましいでしょう。
FP(ファイナンシャル・プランナー):
FPは適切な専門家とのコネクションを持っていて様々な相談の窓口となってくれます。税金・法律・書類の作成など多岐に渡る相談はFPを窓口にするとスムーズです。
行政書士:
遺言書の書き方の指導や公正証書の作成は行政書士に依頼することができます。公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する際の証人として任命したり、相続開始まで遺言書を保管してもらうこともできます。
税理士:
相続税対策、相続税の計算や、節税方法など、税金に関する相談は税理士に相談できます。
弁護士:
相続に関する法律的な問題の解決や相談は弁護士に依頼しましょう。